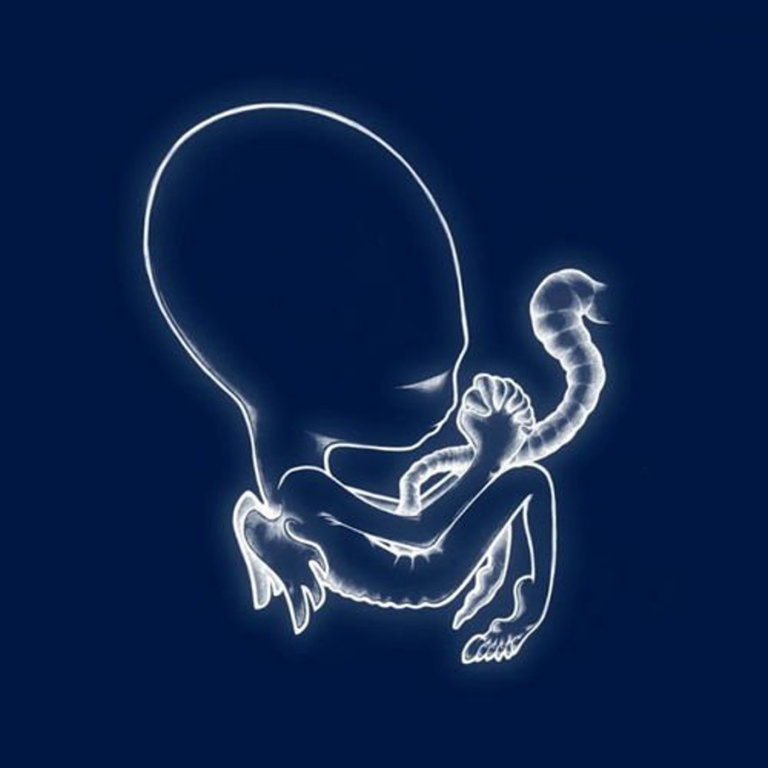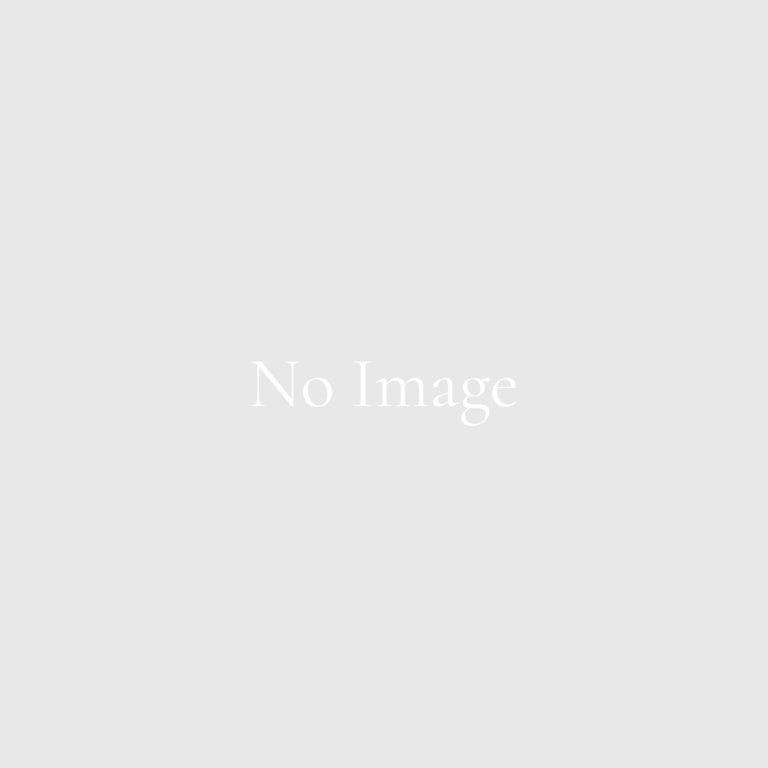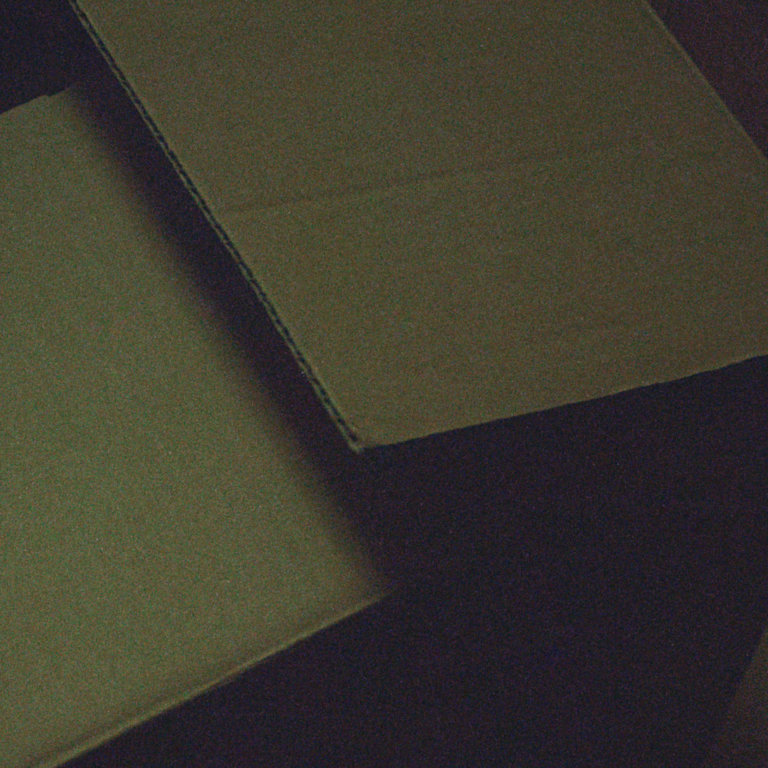NEWS
[.que]出演のプラネタリウムライブ『星空ごこち2024』7年目は3/3(日)に開催
2024.01.05

新宿コズミックセンターの8Fプラネタリウムにて、『星空ごこち 2024 プラネタリウムライブ』の開催が決定。2024年3月3日(日)の昼公演となる。

本イベントはorange plus musicが企画するプラネタリウムライブで、7年続けての開催となる。新宿の小さなプラネタリウムで、満点の星空の下、穏やかな音楽に包まれる時間を過ごすことができる。音響は大場傑(no.9 orchestra)、フライヤーデザインは菅野友美が担当。
今回は2019年、2021年と過去2回『星空ごこち』に出演している[.que]のワンマン公演として開催。過去2回と比べると、最長の演奏時間が予定されている。2023年12月に開催された自由学園明日館 講堂でのワンマンライブでもorange plus musicが運営協力していたが、それに続いてのワンマン公演となる。

会場は一年を通して様々なプラネタリウムライブが行われる新宿コズミックセンター。星座や恒星など、楽曲に合わせてプラネタリウムの演出を行う。ライブの途中にスタッフによる星空解説も行われる。
定員は130名。申込みは特設Webサイトから行うことができ、2/2(金)締切で抽選となる。
イベント情報
星空ごこち 2024 プラネタリウムライブ
■日程
2024年3月3日(日)
■時間
13:30 開場 / 14:00開演
■出演
[.que]
■料金
¥1,600(事前支払い)
■定員
130名(多数抽選・参加申込は2/2金まで)
■会場
新宿コズミックセンター 8F プラネタリウム
■主催
公益財団法人新宿未来創造財団
■企画
orange plus music
プロフィール
[.que]
徳島県出身湘南在住。幼少期よりギターを独学で学び2010年より[.que]名義で本格的に活動を開始。 新たなる『日本』から発信される才能、フォークトロニカの新星として活動初期より注目され、一聴して伝わるメロディー、美しい楽曲は世界中から大きな賞賛を浴びている。
近年ではインストゥルメンタル作品のみならず、作詞作曲編曲のすべてを手掛け、枠に捕われない自身の音楽性を発揮。作品のみならずCM音楽、空間演出音楽も多く手掛け、その他楽曲提供やリミックスなど活動は多岐に渡り様々なコラボレーションを行っている。
ライブではフェスへの出演、海外アーティストとの共演、また海外ツアーも経験。バンドルーツを感じさせる楽曲、パフォーマンスに魅了される人も多く、さらなる活躍が期待される音楽家である。
常に「今、鳴らしたい音」を表現し続けている。
-
PROJECT 6
2024.04.15

福祉作業所の生活音を楽曲に。セタオーレーベルが世田谷区から広げる、「音楽を聴く」社会支援の形
SDGs文脈でも注目を集めるプロジェクト。福祉領域が持つ課題に、音楽はどう向き合えるのか?
-
PROJECT 5
2024.03.05

音にはドラマがある。歴史ある建物や焙煎の音を、アンビエント音楽へ。FM京都『音の縁側』の制作背景
フィールドレコーディングの音で巡る、京都モダン建築と喫茶の空間。
-
PROJECT 4
2024.02.23

「アンビエント」を通して、社会を捉え直す。7日連続で開催した『MIMINOIMI -Ambient / Week-』を振り返る
「アンビエントとは何か?」を多角的に問い直した音楽イベントの企画背景を伺った
ABOUT
生活風景に
穏やかな音楽を
『Ucuuu』は、穏やかな音楽のある生活風景を紹介するAmbient Lifescape Magazine(アンビエント・ライフスケープ・マガジン)です。
アンビエント、エレクトロニカ、インストゥルメンタル、アコースティックギターやピアノなど、「穏やかな音楽」は日常にBGMのように存在しています。
木漏れ日のように、日常に当たり前のようにありながらも強く認識はせず、でも視線を向けると美しさに心癒されるような「穏やかな音楽」の魅力を多面的に発信しています。